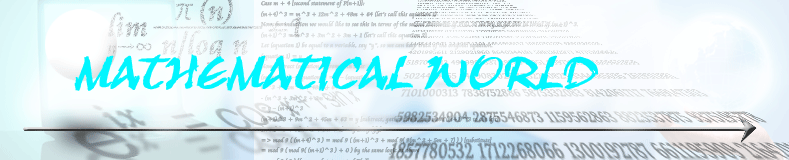
 2次体(Quadratic Field)
2次体(Quadratic Field)
まずは定義から…。
|
定義
|
dを平方因数を持たない(squarefree)有理数とします。 |
Qは有理数全体の集合、Zは有理数の整数の集合のことです。
ここで、次の定理が成立します。
|
定理
|
a,b∈Z とする。αをQ(√d)の整数とすると、 |
(証明)
α=a + b √d とすると、
S(α) = α+α~ = 2a、N(α) = α・α~ = a2-db2
である。
(αは整数)
⇔ 2a∈Z、a2-db2∈Z
このとき、
a2-db2∈Z⇔4a2-4db2∈Z⇔(2a)2-d(2b)2∈Z
∴ 2b∈Z
ここで、2a=x、2b=y とおくと、
a2-db2 = (x2-dy2)/4
⇔ x2-dy2 ≡ 0 ( mod 4 )
このとき、d = 4n + k (k = 1,2,3)とおくと、
x2-(4n+k)y2 ≡ 0 ( mod 4 )
⇔ x2-ky2 ≡ 0 ( mod 4 )
定理でωが特別な形をとるのは、k=1 ( d ≡ 1 ( mod 4 ) )のときであるので、
x2 ≡ y2 ( mod 4 )
となり、x,y がともに偶数なら成り立つし、奇数なら
x2 ≡ y2 ≡ 1 ( mod 4 )
でやはり成り立つことが分かる。つまり、
x ≡ y ( mod 2 )
であればよいわけである。
ここで、
x - y = 2z
とおくと、
α = a + b √d
= (x + y √d)/2
= {(y+2z) + y√d}/2
= z + {(1+√d)/2}y
これは、定理の
d ≡ 1 ( mod 4 ) ならば、ω=(1+√d)/2
の形になっている。
(証明終)
<Q(√-1):ガウスの数体(Gaussian integers)>
ガウスの数体の定義については、上述のとおりです。ガウスの数体の中で、整数の集合を特に、ガウスの整域 Z[√-1] といい、その元をガウスの整数と呼んでいます。
Q(√-1) = {a + b √-1:a,b∈Q}
Z[√-1] = {a + b√-1:a,b∈Z}
<有理整数と整数>
有理整数に関して、素因数分解の一意性というものが存在して、すべての自然数は、その正の素因数の積が一意的に決まるわけでした。これを一意分解定理と呼びます。ここで、素数に1を含めると、1は何回かけても元の数になるので、これは不都合なのです。
有理整数全体に関してはどうでしょう。たとえば、-6の素因数分解は、
-6=2×(-3)
ともかけますし、
-6=(-2)×3
とも書けるわけです。
p が有理素数なら、当然 -p も有理素数になるわけで、これらの組は、同伴素数または同伴といいます。
また、素数でも合成数でもない1や-1は単数と呼びます。
|
有理整数の一意分解定理
|
0以外のすべての有理整数を素因数に分解すると、因数の順序の置き換えや、同伴での置き換えを除くと、一意的に決まる。 |
有理整数の性質の確認を終えたところで、本題である整数の性質を考えていきます。
<整数の単数について>
有理整数の単数はその逆数も有理整数である、つまり±1のみでした。
では整数の単数はどのようなものでしょうか?
|
定義:整数の単数
|
Q(√d)の整数εは、ε|1 のとき単数と呼ぶ。±1は常にQ(√d)の単数である。 |
Q(√-1)のときを考えてみましょう。
ε = a + b√-1 (a,b∈Z)として、
N(ε) = a2 + b2 = ±1
とならなければいけないわけですが、明らかに、
a2 + b2 > 0
なので、
N(ε) = a2 + b2 = 1
このとき、
(a,b) = (1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)
の4通りあり、Q(√-1)のとき単数は、±1と±i の4つとなることがわかります。
次にQ(√-3)のときを考えてみましょう。
-3 ≡ 1 ( mod 4 ) なので、
ε = a + bω (a,b∈Z) ω=(1+√-3)/2
とおくと、
N(ε) =εε~
=(a+bω)(a+bω~)
=a2 + (ω+ω~)ab + (ωω~)b2
=a2 + ab + b2
=(a+1/2・b)2+3/4・b2
>0
より
a2 + ab + b2 = 1
⇔( 2a + b )2 + 3b2 = 4
∴3b2 < 4 ⇔ b2 < 4/3 ⇔ b = 0,1,-1
b=0 のとき、a=±1
b=1 のとき、a=0,-1
b=-1 のとき、a=0,1
以上より、
ε = a + bω (a,b∈Z) ω=(1+√-3)/2
に、(a,b)=(1,0),(-1,0),(0,1),(-1,1),(0,-1),(1,-1)を代入したもの
±1,±(-1+√-3)/2,±(-1-√-3)/2
がQ(√-3)の単数となる。
d ≠ -1,d ≠ -3 (d<0)のときを考えてみましょう。
まず、d=-2のときは、
ε = a + b√-2 (a,b∈Z)として、
N(ε) = a2 + 2b2 = 1
とならなければいけないわけです。このとき、|b|≧1なら左辺は2以上になるためb=0である必要があります。そのとき、a=±1です。
次に、d≦-5 (d=-4のときは二次体ではない。)のときも、
ε = a + b√-d (a,b∈Z)として、
N(ε) = a2 + db2 = 1
となり、b=0である必要があります。そのとき、a=±1です。
つまり、d ≠ -1,d ≠ -3 (d<0)のとき単数は±1です。
以上をまとめると、
|
Q(√d) (d<0)の単数
|
d = -1 のとき、±1,±i |
<素数と有理素数>
有理整数の素数は、0、単数以外でそれ自身とその同伴および、単数のみで割り切れる数と定義できます。同様にQ(√d)の素数も定義できますが、そのまえに、Q(√d)の同伴を定義しておきましょう。
|
Q(√d)の同伴
|
Q(√d)の0以外の整数α、βについて、α/βが単数になるときαはβの同伴である。 |
|
Q(√d)の素数
|
0、単数以外でそれ自身とその同伴および、単数のみで割り切れる数。 |
有理数の素数は、Q(√d)の素数と区別するために、有理素数と呼びます。
|
定理
|
αをQ(√d)の整数とし、N(α)が有理素数のとき、αは素数である。 |
<一意分解整域(UFD unique factorization domain)>
既約元、素元について…。
|
既約元(irreducible element)
|
Q(√d)の整数の0でも単数でもない元aを、a= bc (b,c∈Q(√d))と分解したとき、b または c のどちらかが必ず単数となるとき、aを既約元といいます。 |
|
素元(prime element)
|
Q(√d)の整数の0でも単数でもない元aが、 a|bc ならば必ず、a|b または a|c となるとき、 a は素元(prime element)といいます。 |
有理整数Zにおいてこの両者は同義でしたが、2次体においては一般に異なります。
まず定義から…。
|
一意分解整域
|
Q(√d)の整数全体の集合が、その任意の元αに関して、既約元の有限積として一意的にあらわされるとき、一意分解整域といいUFDとかく。 |
一意分解整域である2次体は、Q(√d)のdがどのようなときなのでしょうか?
実は虚2次体における一意分解整域をQ(√d)は次にあげるもののみとなることがアメリカのスタークとイギリスのべーカーによってそれぞれ独立に示されています。
|
虚2次体における一意分解性を持つd
|
|
d=-1,-2,-3,-7,-11,-19,-43,-67,-163の9個のみ。
|
ちなみに、実2次体における一意分解整域は有限か無限かすら分かっていません。
続く…
